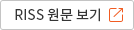인용/피인용
' 겐로쿠아코(元祿赤穗) 사건의 문화사적 전개 연구' 의 참고문헌
-
林亮勝「德川綱吉」, (西山松之助,『圖說忠臣藏』), 河出書房新社, 1998.
-
폴 발리『일본문화사』경당 [2011]
-
코헤이 저, 정지욱 역『일본 양명학』
-
일본영화시대성
-
일본 근세의 공공적 삶과 윤리
-
와타나베 히로시 저, 박홍규 역『주자학과 근세일본사회』예문서원 [2007]
-
료엔 저, 박규태, 이용수 역 『도쿠가와 시대의 철학 사상』
-
黑石陽子「仮名手本忠臣蔵の作家たち」(服部幸雄『仮名手本忠臣蔵を読む』), 吉川弘文館, 2008.
-
黑住眞 『近世日本社會と儒敎』, ペリカン社, 2003.
-
高田祐介「明治維新「志士」像の形成と歴史意識:明治二五・二六年靖国合祀・贈位・叙位遺漏者問題をめぐって」, (『歴史学部論集』), 仏教大学歴史学部論集, 2012.03.
-
高橋富雄「仇討讚美と日本人」, (『忠臣藏と日本人の仇討』) 公中文庫, 1999.
-
高木昭作『日本近世國家史の硏究』, 岩波書店, 1990.
-
鈴木暎一「藤田東湖の思想--「弘道館記述義」を中心として」, (『日本歴史』) 吉川弘文館, 1982.10.
-
野田彦四郎「安藤昌益論著「自然真営道」における「大序巻」ならびに「真道哲論」の現代的意義」, (『名古屋女子大学紀要』), 名古屋女子大学, 1984.03.
-
辻達也「江戶開府」, (『日本の歷史 13』) 中央公論社, 1966.
-
辻岡正己「大久保利通の「富強化」構想」, (『広島経済大学経済研究論集』), 広島経済大学経済学会 , 1988.06.
-
赤穗山鹿素行硏究會編『赤穗義士と山鹿素行』, 赤穗山鹿素行硏究會, 2010.
-
谷口眞子『赤穗浪士の實像』, 吉川弘文館, 2006.
-
谷口眞子「武士道と士道-山鹿素行の武士道論をめぐって」, (『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第4分冊) 早稲田大学大学院文学研究科, 2013年 2月.
-
谷佳憲「宣長文学論への一視角 : 山鹿素行と本居宣長」, (『学習院大学大学院日本語日本文学』5号), 早稲田大学大学院文学研究科, 2009.03.
-
諏訪春雄「忠臣藏の深層」, (『國文學 解釋と敎材の硏究』), 學燈社, 1986 12月.
-
西村玲「聖俗の反転 : 富永仲基」「出定後語」の真相」, (『宗教研究』78(3)), 日本宗教学会, 2004.12.
-
藤井定義「中井竹山と中井履軒の経済思想」, (『大阪府立大學經濟研究』), 大阪府立大学経済学部, 1981.12.
-
菊地明『圖解雜學 忠臣藏』, (ナツメ社, 2002.
-
義太夫年表近世篇刊行会『義太夫年表』, 八木書店, 1975.
-
笠谷和比古「武士道概念の史的展開」(『日本研究』第35集), 国際日本文化研究センター, 2007.
-
竹林庄太郎「海保青陵の商業思想(二)」, (『同志社商学 第27巻』第5号), 同志社大学商学会, 1976.02.
-
竹內誠「赤穗義士事件とは何か」, (西山松之助『圖說忠臣藏』), 河出書房新社, 1998.
-
立川章次「吉田松蔭における行動の理念」,(『駒澤史学』), 駒澤大学文学部史学会, 1986.05.
-
磯前順一「〈日本宗教史〉を脱臼させる--研究史読解の一試論」, (日本宗教学会偏『宗教研究』) 日本宗教学会偏, 2008.09
-
石岡久夫『山鹿素行兵法學の史的硏究』, 玉川大学出版部, 1980.
-
田口章子『歌舞伎と人形浄瑠璃』, 歷史文化ライブラリ, 2004.
-
田原嗣郞『赤穗四十六士論 - 幕番制の精神構造』, 吉川弘文館, 2006.
-
玉懸博之『近世日本の歷史思想』, ペリカン社, 2007.
-
犬丸治「南北〮, 默〮〮阿弥の「忠臣蔵」とその時代」, (服部幸雄『仮名手本忠臣蔵を読む』) 吉川弘文館, 2008.
-
源了円『義理と人情』, 中央公論社, 1974.
-
渡部武「石田梅岩の経済倫理思想の妥当性について」, (『跡見学園女子大学文化学科紀要』21), 跡見学園女子大学, 1988.
-
渡邉憲正「自由民権論の思想構造:--植木枝盛(1857-92)の理論的「転換」に即して」, (『関東学院大学経済経営研究所年報』36), 関東学院大学経済経営研究所, 2014-03.
-
渡辺憲司「山鹿素行と国文学」, (『日本文学研究』14号), 日本文学研究, 1978.
-
浅野秀剛「浮世絵「忠臣蔵」製作とその背景」, (西山松之助『圖說忠臣藏』) 河出書房新社, 1998.
-
河竹登志夫 「「忠臣蔵」の成立」, (『歌舞,技』) 1979 2月號
-
河上澈太郞『吉田松陰』, 中央公論社, 1979.
-
池波正太郞「元禄快擧のついて」, (池波正太郞他編『忠臣藏と日本の仇討』), 中公文庫, 1999.
-
森田健司「石門心学史における手島堵庵の思想的位相--外形的制約からの決別と「本心」」, (『大阪学院大学経済論集』), 大阪学院大学経済学会, 2010.
-
森田健司「中沢道二の「道話」哲学にみる存在論的転回--石門心学隆盛の時代とその真因」, (『大阪学院大学経済論集』), 大阪学院大学経済学会, 2010
-
棚橋正博「山東京傳の世界」, (『江戶戱作草紙』) 小學館, 2000.
-
桐原健真「幕末維新期における自他認識の転回--吉田松蔭を中心に」, (『年報日本思想史』) 日本思想史研究会, 2002.03.
-
松島泰勝「本居宣長における内発的発展論の展開」, (『早稲田経済学研究』), 早稲田大学大学院経済学研究科経済学研究会, 1993.
-
松島榮一『忠臣藏』, 岩波書店, 1964.
-
東晋太郎「三浦梅園に於ける哲学と経済」, (『経済学部研究会 The journal of economics of Kwansei Gakuin University』), Kwansei Gakuin University, 1950.9.
-
杉畠孝博「山片蟠桃の絶対主義思想について : ブルジョア・イデオロギストの系譜」, (『金城学院大学論集』) 金城学院大学, 1962.
-
服部幸雄「仮名手本忠臣藏のすべて」, (西山松之助『圖說忠臣藏』), 河出書房新社, 1998.
-
日高昭二 『近代つくりかえ忠臣藏』, 岩波書店, 2002.
-
折原裕「江戸期における商利肯定論の形成 : 石田梅岩と山片蟠桃」(敬愛大学敎授『敬愛大学敎授論叢』(敬愛大学, 1992)
-
手島勝彦「石田梅岩(石門心学)の「都鄙問答」にみる経営理念について」, (『広島経済大学創立三十周年記念論文集』) 広島経済大学経済学会, 1998.
-
後藤陽一外『日本思想大系30 熊澤蕃山』, 岩波書店, 1971.
-
座藤忠男『日本映畵史 1』, 岩波書店, 2006.
-
島薗進「宗教学の成立と宗教批判 : 富永仲基・ヒューム・ニーチェ」, (『宗教研究』) 日本宗教学会, 2008.09.
-
岩瀬忠篤「「心学」の石田梅岩」, (千葉大学総合政策学会『千葉大学経済研究』), 千葉大学総合政策学会 Vol.18, 2004
-
岡村光章他「江戸期以前日本出版文化史年表--国立国会図書館所蔵資料を中心に」(岡村光章他『参考書誌研究』41号). 国立国会図書館, 1992.
-
山鹿素行, (『日本思想大系 32, 山鹿素行』), 岩波書店, 1979.
-
山本敦司, 中野元『敎科書が教えない忠臣藏』, 扶桑社, 1999.
-
山本博文『ナナメ読み忠臣蔵』, NHK, 2008年 12月.
-
山本博文 『ななみ読み忠臣藏』, NHK, 2008.
-
山井湧 校注, (『日本思想大系 29 中江藤樹』), 岩波書店, 1974.
-
尾藤正英『日本の國家主義-「國體」思想の形成』, 岩波書店, 2014.
-
小見山隆行「我が国の商業教育の変遷と商業道徳の考察」, (『愛知学院大学論叢. 商学研究』47) 愛知学院大学商学部, 2006.
-
小沢富夫『歴史としての武士道』, ペリカン社, 2005.
-
宮澤誠一『近代日本と『忠臣藏』幻想』, 靑木書店. 2001.
-
大野晋「解說」, (大久保正 編集『本居宣長全集』第 1卷), 筑摩叢書, 1993.
-
大谷時中「人間形成に於ける自然の解釈 : その一三浦梅園の玄語に縁りて」(『茨城大学教育学部紀要』), 茨城大学教育学部, 1964.
-
大江志乃夫『國民敎育と軍隊』, 新日本出版社, 1974.
-
大久保純一「忠臣蔵のと浮世絵」, (服部幸雄『仮名手本忠臣蔵を読む』) 吉川弘文館, 2008) p.219.
-
堀勇雄『山鹿素行』, 吉川弘文館, 1987.
-
坪内逍遥, 綱島梁川 共編『近松の研究』春陽堂, 나 [1900]
-
坂本保富「佐久間象山の洋学研究とその教育的展開 : 幕末期における軍事科学を媒介とした洋学の普及現象」, (『教職研究』) 信州大学全学教育機構教職教育部, 2011.06.
-
國立劇場藝能調査室『國立劇場上演資料集68 東海道四谷怪談』, 國立劇場調査養成部藝能調査室, 1971.
-
國立劇場藝能調査室『仮名手本中心蔵 上演年表』(近代の部), 國立劇場, 1986.
-
國立劇場藝能調査室『仮名手本中心蔵 上演年表』(近世の部), 國立劇場, 1986.
-
國立劇場藝能調査室『仮名手本中心蔵 上演年表』(明治の部), 國立劇場, 1986.
-
四方田犬彦『일본영화의 이해』현암사 [2000]
-
吉田俊純「荻生徂徠の経済論」, (『筑波学院大学紀要』), 筑波学院大学紀要, 2015.
-
吉成勇編『「忠臣藏」のすべて』, 新人物往來社, 1992.
-
吉川弘文館編輯部偏『日本近世史年表』, 吉川弘文館, 2007.
-
古結諒子「華夷秩序と帝国主義」(『比較日本学教育研究センター研究年報』Vol.11) お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター, 2015.03.
-
北野雄横「井小楠と「書経」 : なぜ「二典三謨(ぼ)」の篇を重んじたのか」(『大阪産業大学論集. 人文・社会科学編』) 大阪産業大学, 2015.02
-
北田耕也「「明六社」啓蒙思想について-明治社会教育思想の源流」(『明治大学社会教育主事課程年報』) 明治大学社会教育主事課程年報, 1992.03.
-
加藤秀俊 「忠臣藏における葛藤解決」, (『國文學ー 解釋と敎材の硏究』), 學燈社, 1986 12月
-
前田勉「山鹿素行における士道論の展開」, (『日本文化論叢』), 愛知教育大学日本文化研究室, 2010.
-
前田勉「山鹿素行「中朝事実」における華夷観念」, (『愛知教育大学研究報告 人文・社会科学編』), 愛知教育大学, 2010.
-
利根川裕「幕府への恭順と挑戰」, (『忠臣藏と日本の仇討』), 中公文庫, 1999.
-
元祿忠臣藏の會『元禄忠臣藏 データ ファイル』, 新人物往來社, 1999.
-
佐藤忠男, 『忠臣藏-意地の系譜』, 朝日選書, 2003
-
佐藤堅司「「武士道」といふ語の起原と發達:「武士道思想の發達」を傍系として」, (『駒澤地歴學會誌』2) 駒澤地歴學會誌, 1939.
-
佐伯有義外編『武士道全書』2, 時代社, 1942.
-
佐久間正『德川日本と思想形成と儒敎』, ぺりかん社, 2007.
-
今岡謙太郞「仮名手本忠臣蔵と大衆文化」, (服部幸雄『仮名手本忠臣蔵を読む』), 吉川弘文館, 2008.
-
今尾哲也 「荻生徂徠 - 御側用人柳沢出羽守吉保儒臣」, (西山松之助『圖說忠臣藏』), 河出書房新社, 1998.
-
今井淳, 小擇富夫『日本思想論爭史』, ペリカン社, 1980.
-
今中寬司外編『荻生徂徠全集』第6卷, 河出書房新社, 1973.
-
井上哲次郎『武士道』, 兵事雑誌社, 1901.
-
丸山眞男『丸山眞男講義錄』, 第7冊(東京大學出版會, 1998.
-
中江克己『忠臣藏と元祿時代』, 中公文庫, 1999.
-
中山廣司, 『山鹿素幸の硏究』, 神道聞學會, 1988.
-
下中弘編「國體思想」, (『日本史大辭典(全7卷)』), 平凡社, 1992.
-
上村以和於 「仮名手本忠臣蔵」, 慶應義塾大學出版會, 2005.
-
三枝博音編「多賀默卿君に答ふる書」, (『三浦梅園集』) 岩波文庫, 1953.)